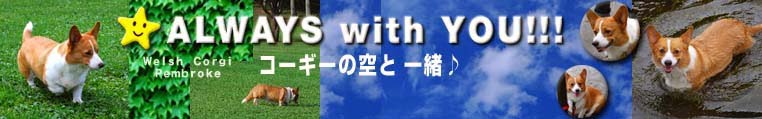枚方大橋の一本西側「柱本大橋」から眺めた大阪市内の
様子、比較的高い建物が遠くに見える。
淀川は電車が開通するまでの間、交通の要として
京となにわを結ぶ水運が栄えていた。
しかし、鉄道の発達とともにその役目は次第に終わりを告げた。
鉄道唱歌55番
淀の川舟さをさして (よどのかわぶねさをさして)
くだりし旅はむかしにて (くだりしたびはむかしにて)
またたくひまに今はゆく (またたくひまにいまはゆく)
煙たえせぬ陸の道 (けむりたえせぬくがのみち)
東海道本線全通 1889(明治23)年、新橋から神戸までの東海道本線が全線開通した。
淀川を外輪船が走っていたことを知る人は少ない。
高槻のある旧家で、わたしは外輪船の写真を見せてもらった。
まるでSL機関車のようにモクモクと黒煙を吐き出しながら
河を上ってゆく写真に目を奪われた。
昭和のはじめの写真で、それは写真フィルム以前の「ガラス乾板」
で撮られた写真だった。
*ガラス乾板/光に感光する銀塩の乳剤を透明のガラス板に塗布したもの。
この大正始め生まれの作者は、趣味で写真をしていた訳ですが
当時の写真としては珍しく、農村風景・外輪船・商店街など
ごく日常の風景を写真に収めていました。
時代を経て見る私たちには、一時代前のごく普通の風景なのに
記録としての大きな価値を認めざるを得ませんでした。
目を向けよう、いま目の前にある「日常の世界」
美しい写真は世の中に何百、何千とあります。
それらが真に美しいと思わせるのは、
文化や時代が複雑に絡みあっているからだと思います。
何が記録されてきたか、いつどこで撮られたか歴史は写真作品の
重要性を測る大切な要素でもあると思う。▼・エ・▼


いま、大阪から京都までJR新快速で30分。流れを遡る「外輪船」は
想像ではあるが4時間あまりの時間を費やしたかもしれない。
大阪でもあちらこちらで、水辺の再開発が行われている。
大阪の道頓堀あたりから、新淀川〜桂川〜鴨川を経由して京都まで
船の旅ができないものだろうか?要所要所に船着き場などをつくり水辺の
茶屋でくつろげるなんて風流だと思うのだが…。

▼・エ・▼
Please assist and click my site.